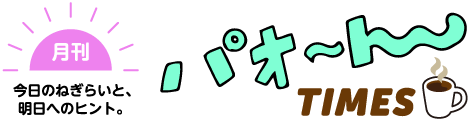
VOL 26|2025年09月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~
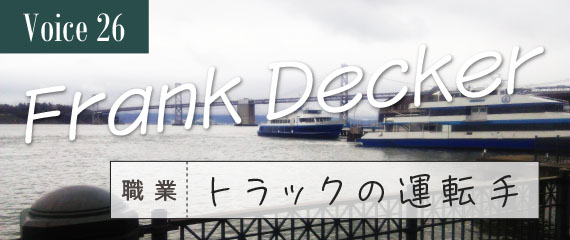
ゲイリー(米国インディアナ州北西部にある工業都市)からウィスコンシン州(米国中西部の北部に位置する州)まで鉄を運んでいた。業界では、半径およそ150マイル(約241km)のこの輸送は短距離。彼は1949年、19歳のときからこの仕事に従事していた。
「数えてみたんだけど、輸送した回数は2,500回だった。いかにも退屈な響きじゃないか?
夕食後に鉄工場へ行くんだ。夜間に荷積みをするんだけど、たいていは長時間待つことになる。組合ができるまでは特に長かったね。荷積みが終わるまでに長くて12~14時間待ったものだよ。輸送会社がその待ち時間分を工場に請求することはない。貨物列車と同じ扱いだよ。
僕らがどんなに労力を注ぎ込んでも、給料は変わらない。僕らを待たせたからと言って、輸送会社がその分の賃金を出すわけじゃないから、工場にも何も請求されないんだよ。彼らはずっと僕らを酷使してきたんだ。
退屈で頭がおかしくなってしまわないようにしなくちゃならない。時間が経つにつれて慣れてくるよ。4時間、8時間、12時間。忍耐力をつけるのも仕事のうちだね。トラックのキャビンに座る。売店まで半マイルほど歩いて、ラップで包んだサンドイッチやコーヒーをテイクアウトする。工場内の荷積み担当者のデスクあたりに座って、クレーンを眺める。雑誌を読む。4時間くらい寝る。
運転手たちは他の男たちと同じように女性について話すけど、現実じゃなくてあくまで夢物語なんだよね。ずっと移動してるから、遊ぶ機会を奪われてるんだ。
それで、トラック運転手は巨大な何かを妄想しがちだよね。コーヒーショップに立ち寄るやいなや、その妄想を一気にぶちまけるんだ。そんな妄想を抱いてドライブインにやって来た運転手たちを知ってるよ。彼らはその妄想を話し出すんだけど、30分もかけて、生き生きと描写してみせるんだ。そして突然何かが足りないことに気づいて、その物語が自分の脳内で膨れ上がった馬鹿馬鹿しさの塊だったと理解するわけさ。」
~今月のリアルヴォイス~
“. . . and all of a sudden come up short and realize it’s all a bunch of damn foolishness they build up in their minds.”
(そして突然、何かが足りないことに気づいて、それが自分の脳内で出来上がった忌々しくて馬鹿馬鹿しい塊だったと理解するんだ。)
*all of a sudden=突然、*come up short=一歩及ばない・達成できない
*a bunch of=大量・たくさん、*foolishness=馬鹿馬鹿しさ・愚かさ
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 279-296.

~フロイト博士の処方箋~
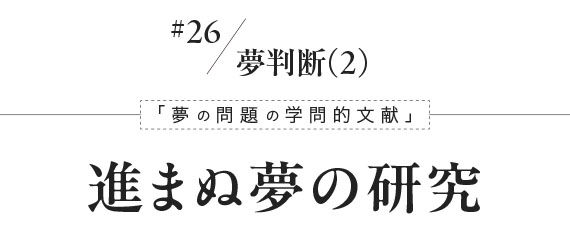
フロイトがこの『夢判断』で目指したことは次の2つである。
第一に、夢にはそれを解きあかす方法があり、その方法を用いれば、夢とは人間の心の表れであると納得できるようになること。第二に、夢はなぜ奇妙でとりとめのないものなのか、その理由を説明して、人間の心が持っているいろいろな力の正体を突き止めること。
つまり彼は、謎に満ちた目に見えない「心」に対し、同じく謎に満ちた「夢」を糸口にして、「再現可能な解釈方法」と「半永久的に作用している力」を明らかにすることで近づきたかったのである。
そこでさしあたりフロイトは、従来、学問的に夢の問題がどう捉えられてきたのか、歴史を振り返りながら過去の研究を取りあげている。
古代、ギリシア、ローマ民族は、夢とは、彼らが信仰する超人間的存在と関係するものと考えていた。さらに、夢が未来を予言するものと考えはじめたのも彼らであった。
彼らにとって夢は大きく分けて2種類あった。それは、神のお告げなどを意味する「本当に価値ある夢」と、「価値のない、まやかしの、くだらない夢」である。しかしながら、すべての夢について価値の有無をそうやすやすと判断できるわけではない。こうした事情が、夢をもっと別の、筋の通った、意味深い内容に置き換えようという学問的努力につながったのである。
その後出てきたアリストテレスは、夢をすでに心理学の研究対象とみなしていた。夢は人間精神から発するものであり、人が眠っている間の「魂のはたらき」と定義された。
さらにアリストテレスは、夢というものの具体的な特徴にも注目していた。たとえば、「体のどこかがほんのちょっと温かくされると、火の中を通って熱く感ずるというような夢を見る」という場合である。このことからアリストテレスは、医者が、昼の間は気づかれないような体内の変化の最初の兆候を夢によって推知できるだろうと結論づけた。
それから長い時を経たにも関わらず、古代の人々のように夢を超自然的な世界の表れだと信じる者は、フロイトの時代にもまだ存在していた。心理学的な説明が、集められた材料のすべてを消化しきるまでには至っていなかったのも、その原因の一つである。
夢の研究は、他分野の研究のようにいくつもの時代を通して同じ方向にそって積み重ねられ、進化していくことなく、ただその時々で同じような場所を行きつ戻りつしていたのである。
【参考・引用文献】
ジークムント・フロイト著、高橋義孝訳
『夢判断(上)』(1969年、新潮社)
pp. 11-19.