
VOL 15|2024年09月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

雑誌『ニューヨーカー』の映画評論家。
「映画で仕事が描かれることはめったにありません。『恋愛手帖』という映画にはそのシーンがひとつだけあります。すごくいいシーンというわけではありませんが、仕事について話す人たちが描かれていて、驚かされます。状況が状況なので、たとえどんな出来でも、あらゆるタイプの働くシーンが記憶に残るんです。『街は春風』にも仕事のシーンがありましたね。
映画では理想的な職業ばかりが取り上げられます。ウェイトレスを登場させたら、観客自身が貶されたような気持ちになるんです。ウェイターになりたいとか、清掃会社を経営したいとか言う子供はいませんから。映画においては、ホワイトカラーの仕事に就いていない人たちを描くと、観客をおとしめてしまうことになる。結果的に、映画に出てくるようなアメリカ人と同じ人生を送れない人たちは、自尊心を削がれてしまうことになるんです。
働く中で時おり得られるであろう、俳優や作家たちの満足感が、スクリーン上に表れることはありません。退屈な仕事に従事している観客は、俳優たちを見て、彼らはたくさんお金をもらっているんだと思って楽しんでいますよね。でも、そんな観客たちが本当に羨むべきなのは、俳優や作家が仕事自体から喜びを得ているということなんです。
社会がそのことを軽視しています。私が思うに、テレビCMにも大きな責任があって、それらは、貧しい子供たちに向けて、将来お金を稼ぐために学校に行きなさいと伝えます。きちんと教育を受けたらより満足のいく仕事ができるとか、より自分の能力を発揮できるとか、より人々の助けになれる、とは決して言わないのです。」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 216-218.

~フロイト博士の処方箋~
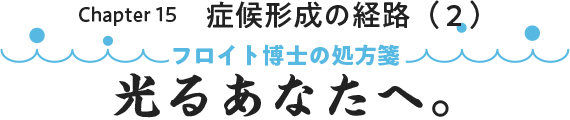
「物語」が世の中を動かす
私の今の楽しみのひとつになっているのが、放送中の大河ドラマ『光る君へ』です。まだ貨幣も流通していない平安時代、現代とはまったく異なる社会を生きる人々の姿は、一見とても遠いようで、不思議と強い親近感を覚えます。
特に、紫式部が藤原道長に請われて『源氏物語』を書き始めてからの展開は目が離せません。貴族たちが「物語」に夢中になり、夢中になればなるほどそこに「自分自身の真実」を見出し、そしてそれが実際に現実を、ひいては世の中を動かしていく様子にため息が出ます。
混じりあう現実と虚構
現在の資本主義の世の中では、合理性や効率ばかりが重視されて見えづらくなっているかもしれませんが、精神分析的には、このように現実とフィクションを行き来することは、じつはとても人間的なことだと言えます。だからこそ私も親近感を抱くのです。
前回、このコーナーでリビドーの進む道をたどりました。神経症とは、現実原則によって満足を阻止されたリビドーが、より以前の時代へ退行することによって、満足の代理物を作り出すことでした。
したがって、神経症を治癒するためには、分析によって以前の時代、つまり幼児期の体験をつまびらかにしていくことになります。分析の方法は、患者が思い浮かぶままに分析者に話をする「自由連想」です。ところが、ここで問題が生じます。分析の中で患者が話す体験は真実なのか、それとも空想なのか、という問題です。実際のところ、「真実に虚偽が多量に混りこんでいる」のだとフロイトは言います。
物的な現実性と心的な現実性
もちろんフロイトは、現実と虚構とは「雲泥の差がある」と述べていますし、精神分析においても、それらは「全く別の評価を受けて」いると断言しています。そんなふうにわざわざ強調せずとも、患者も含め誰もがふつうにそう認識しているはずです。にもかかわらず真偽混じりあった体験が話されるのは、そもそも人間が現実を軽視し、現実と空想との間の区別をなおざりにしてきたからです。
このような状況を受けて、フロイトは、さしあたってはその区別を気にかけず進めよう、と提案します。
「このようにすることは、やはりこれらの心的な産物に対する唯一の正しい態度であることは明らかです。これらの心的な産物もまた一種の現実性を持っているのであって、患者がこのような空想を生み出したということは、あくまでも一個の事実であり、この事実は神経症に対して、患者がこれらの空想の内容を実際に体験した場合とほとんど変らないだけの意義を持っているのです。これらの空想は、物的な(materiell)現実性とは違った心的な(psychisch)現実性を持っているのであって、神経症の世界においては心的現実性こそ決定的なものであるということを理解するようになるのです。」
黒か白か、ではない世界で
社会が複雑化するにつれて、‟現実”もまた複雑化したのです。「人間は、今なお快感動物であるかと思うと、今度は再び知性的な存在に戻るというように、交互に移り変わることができる」ようになったのであり、その都度世界の見え方が変わってくるのは当然のことです。
いまや重要なのは、快感か現実か、真実か虚偽か、正確に見分けてどちらかを選び、どちらかを捨てることではないのかもしれません。そのような質的な区別を前提としながら、どこにどのくらいのエネルギーを充てるか、いつどんなふうに移り変わるかといったバランス感覚が重要なのではないでしょうか。
日々、犯人探しや正しさにとらわれたり、窮屈な損得勘定に振り回されてしまいそうになる世の中ですが、「現実か虚構かは、さしあたっては気にかけないようにしよう(言ってしまえばどちらも現実なのだから)」というフロイトや、惜しげもなく物語に没入し、その強い気持ちで目の前の人生に向き合う平安時代の貴族たちの姿に、はっとさせられる今日このごろです。
【参考・引用文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 184-212.