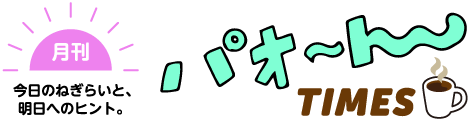
VOL 18|2024年12月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

自動車の組立て工場で熟練工(多能工)に従事して17年目、37歳、男性。イリノイ州とインディアナ州の州境沿いの高速道路にほど近いトレーラー。その狭苦しい住居に、妻と、14歳の息子と13歳の娘と暮らしている。犬がぶらぶらとあてもなく出たり入ったりしている。棚にある古くてぼろぼろの聖書が、見る限りこの家にある唯一の書物である。
「今週2日間は大変でした。作業員の欠勤が続いたんです。誰かが休んだときは多能工である私たちがその代わりをします。
ここにも若い世代が入ってくるようになって、彼らの多くは独身でまだ落ち着いておらず、その日暮らしなんです。彼らも落ち着けば私みたいになると思うのですが。朝起きて、日課をこなし、毎日仕事へ行くようにね。私も、仕事に行きたくなくて家にいたい気分のときもありますが、行ってしまえば気分は上向くとわかっているので、こうやって毎日出勤しています。
会社はパンとバターを食卓にもたらしてくれます。私は10代の子供を含む家族を養っていて、彼らには欲しいものがたくさんあるのです。車2台のローンもありますしね。だから私は1週間に40時間分の給料を家に持って帰っているんですよ。
仕事に慣れてきたら近道ができるようになりますよね。すると突然担当者が来て、私の作業時間を計測するのです。彼が「あなたは1時間のうち56分しか働いていませんね」と言うので、私は「一日中張りつめて作業をしてるんだ、厳しすぎるよ」と言うのですが、会社は時間いっぱい作業をしろと言うだけです。
(インタビュアー:もし車がロボットで製造できるようになって、人間は自分が一番やりたいことをして生活していけるようになったら、どうしますか?)
ガソリンスタンドや食料品店を開いたり、川岸に座って釣りをしたり、あるいは怠け者になったり、そうでなければヒッピーになったり、何もしなかったりすることもあるかもしれません。国民の30%くらいはヒッピーになるんじゃないでしょうか。
あと13年会社にいれば勤続30年になります。退職したら小さな庭を持ちたいです。ちょっとした釣りや狩りをして、腰かけながら太陽が昇ったり沈んだりするのを見ていたいですね。心や頭の中をそんなことでいっぱいにしていたいです。」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 232-239.

~フロイト博士の処方箋~
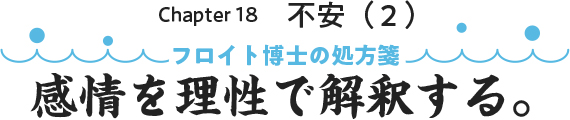
わけのわからないモヤモヤした不安。生きてればこんなこともあるさとやり過ごそうとしてみても、気づけばそれに思いっきり振り回されていた…なんてことも。たびたび襲ってくるこんなやっかいな感情と、どう付き合っていけばいいのでしょうか。
不安にはどのような種類があるのでしょうか。フロイトが挙げているのは3つです。
第一は「予期不安」ないし「不安な予期」です。この種の不安に悩まされる人は、あらゆる可能性のうちから、常に最も恐るべき可能性にとらわれ、すべての偶然を不吉な前兆と見なし、不確かなことはすべて悪い意味に解釈してしまいます。
第二に「恐怖症」の不安が挙げられます。第一の不安とは違い、ある種の対象や状況に結びつけられています。わかりやすいところで言えば、暗闇、蛇、鋭くとがった先端、密室、人込み、孤独、等々。恐怖や不安を抱かせるこれらの対象や状況は、不安とまではいかなくとも、たいていの人にも不気味さや危険を感じさせます。つまり、このタイプの不安は、その内容というよりはその強度の問題になります。
第三に、「理解しがたい不安」があります。たとえば、屈強な大人の男性が故郷の町の道路や広場を通れない、または、いたって健康な大人の女性が、猫が洋服の裾のところでじゃれたからといって、気が遠くなるほどの不安に陥ったりする場合などです。
さて、この三つ目の不安は、ほかの二つの不安とは異なり、本人が訴える不安感情と、さし迫ってくる危険との間の関連性が見当たりません。ならば、それはもう不安とは言えないのでしょうか? いいえ、フロイトはそれでも「臨床的および原因的なすべての関係において、〔この第三の不安も他の〕不安と同列におくことができる」と主張します。現時点では理解しがたいとはいえ、さしあたっては、不安がある場合には、その人間を怖がらせるようなものが存在している、と考えるのです。
いかにもフロイトらしい考え方です。神経症の症候に向き合い、無意識的なものからその原因を見出そうとするときにも、彼はまったく同じ態度でした。
精神分析は、失錯行為や夢、ひいては神経症の症候といった、誰もが見落としてしまうくらい取るに足りなかったり、とうてい理解できそうになかったりする現象と真摯に向き合い、“解釈”することで、無意識下の内容をあぶり出しました。
原因がわからず「理解しがたい不安」。生きていくうえで、少なくない人がこんな感情に悩まされ、失敗した経験があるのではないでしょうか? じつはこのようなありふれた“感情”もまた、解釈という“理性”でとりあつかい治癒すべき、精神分析的関心の中心にあるものだったのです。
【参考文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 244-250.