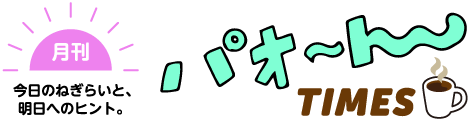
VOL 19|2025年01月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

フォード社に勤めて23年。裁縫の仕事をする妻と、6人の子供がいる。じっとしていられない質(たち)なのか、2階建ての自宅の居間で、人生や仕事について、身振りを交えて表現してくれた。一角には、かつて通っていた高校のバスケットボールチームを優勝に導いた、機敏そうで背の低いフォワード選手の写真が飾られていた。
「トラックのタイヤ部門が最初の職場でした。一日に60~80の仕事をこなしていて、一週間に6日働いていました。時々、自分がロボットになったように感じていましたね。ボタンを押す。決められた方へ進む。仕事が終わればビールを2~3杯飲んで、寝る。日曜日なのに朝起きて仕事に行こうとしたことも一度や二度ではありません。
この仕事が自分の人生全体に影響を与えているんです。自分よりも長く勤めている人たちを見ても、自分と同じか、あるいはもっと悪いくらいです。
もし人生をもう一度やり直せるとしたら、最初の35年間をやり直したいです。私は何にもしていませんでした。働くのが嫌だったんです。近所に住む年配の人の中には、私の母親に会うと、「あの子が働くようになるなんて思いもしなかったな」と言う人がいるくらいです。
今は社内の在庫管理が仕事です。小さな部品を管理していて、求められれば自転車で届けに行きます。給料も下がりました。以前よりもずっと簡単な仕事です。これでいいとは思いませんが、生活のためです。
(インタビュアー:自動車にはその価値があるのでしょうか?)
人から奪い去るものが何であれ、自動車にそれを奪うだけの価値があるとは思いません。しかし、私は、いわゆる誇りといったことについて考えるんです。幹線道路で車が走っている。その車種や持ち主のことは分からなくても、自分の労働をそこに注ぎ込んだ。私のような誰かが、それに仕事を捧げた。そうである以上、それは誇りなんだと思うんです。」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 239-243.

~フロイト博士の処方箋~
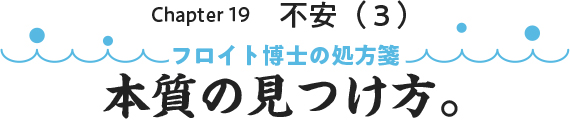
真実か、空想か。この区別をとりあえずわきに置いておくのがフロイトのやり方でした。もちろんこれは「雑」「適当」「無責任」というわけではありません。人間の本質を見つめるためには、このやり方が必要だったのです。
本質とは、リアルのなかにだけあるものでも、フェイクのなかにだけあるものでもなく、その狭間で浮遊しているものであり、こちらが真剣になって見つめ、解き明かそうとしなければ姿を見せてくれないもの。そのためにフロイトは、真実か空想かにこだわらない態度を選びました。
さて、こうした技術は「不安」を考察する際にももちろん発揮されます。
一見、不安を引きおこすようなものが現実に存在しないかのようにみえる「神経症的不安」。これは、満たされなかったリビドーの暴走を恐れた自我が、そのリビドーを外界のものに投射することで発生します。自我は、リビドーの代理物であるその外界のものを危険とみなし、不安を発生させることで、じつのところリビドーから身を守ろうとしているのです。
ここでフロイトが引きあいに出したのは、子どもにおける不安の発生でした。子どもは大人とくらべて頻繁に不安がります。こうした不安は、子どもがまだ弱くて無知なために起こるのだと、お手軽でもっともらしい説明をしてしまいそうにもなりますが、すぐに、この説明は間違っていることに気づきます。
もし、子ども自身の弱さと無知が子どもを不安にさせているのであれば、彼らが危険にさらされないよう周りの大人があれこれ世話を焼くという必要がなくなるはずです。ところが実際には、たいていの子どもは危険知らずで、大人が心配するようなことを何でもやってしまいます。
子どもが見知らぬ人たちに対して不安がるのは、その人たちに悪い下心があると思っていたり、自分の弱さをその人たちの強さと比べたりしているからではありません。フロイトは次のように述べています。
「小児は信頼し愛している人、結局は母親を見ることを目当てにしているのに、見知らぬ人がいるものだから驚くのです。不安に置き換えられるのは、小児の失望と憧れなのです。つまり使用されなくなったリビドーが、もはや浮遊状態のままでいられなくなり、不安となって放出されるのです。」
たとえばこんなやり取りの場合はどうでしょうか。暗い部屋の中でおびえている子どもが隣室に向かって言います。「おばちゃん、ぼくに何か言ってよ。ぼく、こわいよ」。おばちゃんが「ものを言って何の役に立つの。だって、おばちゃんの顔が見えるわけでもないのに」と返します。すると子どもは「誰か何か話してくれれば、あたりが明るくなるんだ」と言うのです。
つまり、このとき子どもの中では、暗闇での(信頼し愛している母親への)憧れが、暗闇に対する不安に変形されていたのです。それゆえ、不安を解消するためには、暗闇そのものを解消するのではなく、ただ、見知っている人がそこにいるという実感さえ持てればよかったのです。
このように、「ほんとうの現実不安は、小児はほとんど持って生まれていないように思われます」とフロイトは言います。子どもの不安は、神経症的不安と同様に、使用されなかったリビドーから生じているのです。
「今や次のように言ってもかまわないでしょう。つまり、恐怖症についてその内容だけを説明しようとして、いろんな事物または任意の状況が恐怖症の対象にされるのはなぜか、ということ以外に何の関心も持たない態度は、いかに不十分なものであるか皆さんにもよくおわかりになったことでしょう、と。恐怖症の内容は、夢に対する顕在性の夢の外観の意義とほぼ同一の意義を恐怖症に対して持っています。」
本質とは、こちらが真剣になって見つめようとしなければ姿を見せてくれないもの、と冒頭に書きました。それは、ガチガチに青筋を立ててものごとを追究するような姿勢とは違うのです。漂うように、何ものにもとらわれない素直な心でものごとを見つめながら、ほかでもない自分の心と向きあう。そんな姿勢から本質が見えてくるのだと、フロイトは教えてくれています。
【参考文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 250-266.