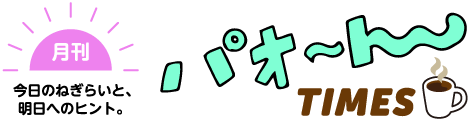
VOL 21|2025年03月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

フォード社の組み立て工場で現場監督に従事。前回登場した工場長のトム・ブランドは直属の上司である。そのブランド氏が外出している間、工場長の椅子に座ってインタビューに答えてくれた。
「おそらくこの工場で私が最年少の工場長です。今はシャシーのラインを担当しています。372人の時間給作業員がいて、13人の現場監督がいます。私はそのトップです。
自分はどんなタイプかというと、もし昇進を受けるべき時期であっても、自分からそれを要求したりはしません。もし上の人たちが私にその資格があると思えば、昇進させるでしょう。もし自分にその価値がなければそうならないだけのことです。上司や会社に自分から聞くことはしません。
休みは取りません。いつも一生懸命働きます。この5年間で3日も休んでいないと思います。そんな私に妻は不満があるみたいですが、たとえば妻が体調を崩したときには、義理の母を家に連れてきて世話をさせ、自分は仕事に行きます。
父も決して仕事を休みませんでした。一生懸命仕事をして、残業もたくさんしました。一日に16時間働いたものです。父は最初、鉄道の構内作業員としてスタートしましたが、今では主任を務めています。会社に人生を捧げていて、私はそんな父を尊敬しています。
仕事に穴があっては絶対にいけません。何年か前に体ごと機械に巻き込まれた男がいました。彼を助け出すためにはラインを止めるしかなく、その時には止めましたけれど。多少の傷くらいは日常茶飯事です。それを何とかするのが私たちの仕事です。
(やがてブランド氏が戻ってきた。インタビューに答えていたウィーラーは兵士のような動きで椅子から立ち上がった。ブランド氏は明るく言った。「彼のような男が2~3人いれば我々はどんなに幸運か。有望な新人だよ。彼みたいなやつらが私たちの仕事を奪う日はそう遠くないだろうな。親切にしておかないと、いつその下で働くことになるかわからないからな(笑)。」ウィーラーは微笑んだ。)」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 249-256.

~フロイト博士の処方箋~
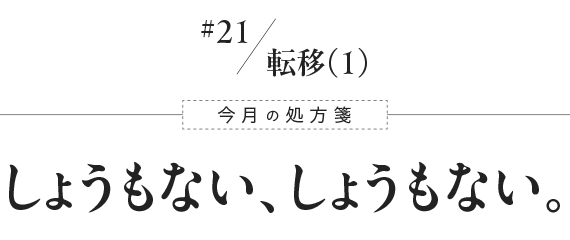
精神分析療法はどんな方法で作用し、どんなことを為すのか。葛藤にがんじがらめになった神経症患者を救いだすためにフロイトが提唱した態度には、誰もが学ぶべき普遍性があります。
是枝裕和監督の映画『怪物』に、こんなセリフがあります。
「そんなの、しょうもない。誰かにしか手に入らないものは幸せって言わない。しょうもない、しょうもない。誰でも手に入るものを幸せって言うの」。
私たちはつい、幸せには“正解”があり、それを手に入れなければ幸せにはなれない、と感じてしまいます。その裏には、「幸せ」と「理想」の混同があります。
フロイトは、それまでの概念をくつがえす無意識の概念をうち立て、性の定義を根本から問いなおしました。そこで明らかになったのは、社会が私たちに要求する「理想」や「道徳」には、実際にそれがもっている価値以上の犠牲が払われているということでした。
フロイトいわく「社会のやり方は真実にもとづいているのでもなければ、賢明さを示すものでもない」。いわば、社会的理想や道徳といった“しょうもない”もののために、大事なものがなおざりにされていたのです。
かくして、「理想」と「真実」との狭間で、人々は葛藤を抱え、時に神経症になるまで苦しみます。しかし、真実はあまりに強く抑圧され、無意識にまで追いやられているため、何もしなければ葛藤が解決されることはありません。
精神分析の目的は、たとえば、抑圧された性的欲求を解放し、「性的に人生を十分享受せよ」とさとすことではありません。相反する二つの傾向のうち一方を支持して他方を追いやっても、何の意味もありません。どちらにしても、常に一方は満足されないままで、葛藤は続きます。
そうではなく、精神分析が目指すのは、無意識的なものを意識的なものに“翻訳”し、葛藤の両端を意識上にのぼらせること。そうやって、解決されえないものだった葛藤を、なんらかの形で解決されるはずの正常な葛藤に変えるのです。
無意識のなかにあるものを探求するにあたって、患者たちは、性的問題も含めあらゆる問題について偏見をもたずに考えるよう促されます。もしかしたら、それが不道徳な態度につながってしまうと危惧する人もいるかもしれません。しかしフロイトは言います。
「教育によって真理を尊重する態度をしっかりと身につけた者は、たとえその道徳の尺度が社会通念となっている基準から何らかのかたちで逸脱しているとしても、不道徳におちいる危険からは常に護られていると言うべきです。」
ネタバレしない程度に書きますが、冒頭にあげた映画『怪物』では、大人たちによって真実や真理がことごとくなおざりにされ、その結果、何よりも大事なものが犠牲となります。何度見ても涙があふれ、胸が苦しくなります。
怪物はつねに私たちのすぐそばにいます。それは、社会が要求する「理想」であり、真実をないがしろにしたうわべの「道徳」であり、それにかんたんに流され巻かれてしまう私たち自身の「弱さ」です。
真実や真理を尊重する態度とその手法を精神分析に学び、日常に活かしていくことで、本当に大切なものを守り続けなくては、と思います。
【参考文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 296-304.