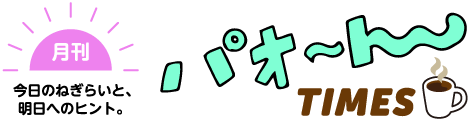
VOL 22|2025年04月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

29歳、男性。会長を務める全米自動車労組(UAW)1112地区には、オハイオ州ローズタウンにあるゼネラル・モータース(GM)社の労働者たちが所属している。「世界で最も自動化された、最も高速の組立ライン」を誇るその工場では、ストライキが“しばしの間”解決にいたったところだった。
「1959年に高校を卒業した後、父の働く製鉄所で仕事を得ました。そこでの4年間、労組の活動に会計係として少しだけ関わりました。最も使える奴だったと思いますよ(笑)。
製鉄所では、組立ラインから始まって、鍛冶のアシスタントや機械工のアシスタントを経験しました。それから機械工にまでなったのですが、63年に解雇されました。組合の活動に本格的に関わるようになったのは、そのあとに就職した工場からです。そして1966年にGMに就職しました。
労働者たちが訴えているのはこういうことです。「私たちは汗もかくし、二日酔いもするし、お腹も痛くなるし、いろんな思いや感情がある。機械と同じじゃない。時計を見ながら指示する者は、ある1分間のことを言っているだけだが、私たちが言っているのは人生の時間のことだ。私たちは普通のことをやるだけだし、何が普通かは私たちがあなたがたに伝える。そこから交渉が始まるんだ。感情の無い時計を基準に始めるつもりはない。」
会社がユニメート〔訳注:1961年に世界で初めて製造された産業用ロボット〕を導入するまでは、1時間当たりの製造台数は60台でしたが、導入で100台に増えました。お祈りしているカマキリのような姿で、作業場から作業場へと次々に移動していきます。疲れることも、汗をかくことも、文句を言うことも、ミスをすることもありません。そして、車を買うこともありません。私が思うに、会社は私たちが何を議論したいか理解していないでしょう。
ここで労働者が幸せを感じることはありません。家に帰りながら、「ああ、今日はいい仕事ができたな。明日また出勤するのが待ちきれないな」と思う人はいないでしょう。かと言って、帰宅してまた出勤するまでの間に、工場に対する不満をあれこれ考える人もいないでしょう。つまり、自分たちの作る製品が良いのか、悪いのか、正確なのか、関心がないんです。
労働者たちは会社が何をすべきか訴えたいわけではないんです。ほかでもない自分たち自身が、何をしていきたいのか。言いたいことがあるとすればただそれだけです。尊厳のある者として接してほしい。求めているのはたったこれだけのことなんです。」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 256-265.

~フロイト博士の処方箋~
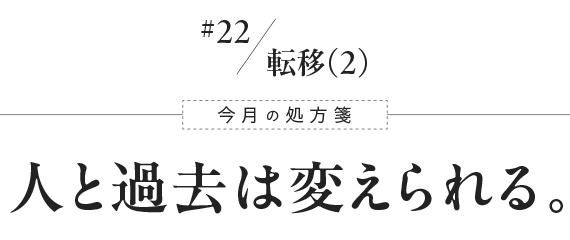
無意識に押しこめられたものを“翻訳”し、意識上に浮かびあがらせること。そうして、解決不可能であった葛藤を、解決しうる葛藤に変えること。それが精神分析の目指すことです。
これは一見「何でもあり」のように思えます。自由連想などの手法を用いて得た材料をもとに、「さあ、信じられないかもしれませんがこれがあなたの無意識の正体です! これで、意味不明なAに悩まされていたあなたの生活は、実のところAとBの葛藤に悩まされていたのだということが分かりました! 悩みはもう解決したも同然です!」と言えば、それで仕事をしたことになるのですから。
言うまでもなく、フロイトがそのような傲慢な人であったならば、そもそも無意識など発見していないでしょう。思い出してください。彼は最初、誰もが見過ごしてしまうような取るに足りない「言い間違い」に目をつけたのです。そんな小さな手がかりから始まって、誰もが投げ出すような面倒で複雑な観察と考察を経て、無意識にまでたどり着いたのでした。
無意識の“翻訳”はけっして独りよがりではない。答えが誰にも分からないその作業が、人を救える理由。
それでは、精神分析は一体どのようにして無意識の“翻訳”を行い、患者を救うのでしょうか。誰にも分からず、神のみぞ知るとしか言えないような「無意識」が、分析者の独りよがりにならずに翻訳されることなど、ましてやそれで被分析者が救われることなど、果たしてあり得るのでしょうか?
患者に耳を傾け、治療を進めていくうちに、フロイトはある奇妙な現象に気づきます。つまり、「苦しい葛藤から逃れる道以外には何ひとつ求めていないはずの患者が、医師自身に対してある特別な関心を抱きだしていることに気づくのです」。
分析を受けている患者が、医師への強い愛情や盲目的な信頼(場合によってはその反対の敵対心)を抱く現象は、新しい症例ごとに決まって繰り返されました。もはや偶然などではなく、「病気自体の本質と最も深いところでかかわり合っている」と考えるほうが自然です。そうして、フロイトはその現象を「転移」と名づけました。
そもそも、患者を悩ます症候の意義は、現実原則によって挫折させられたリビドーが「代理満足」を得ることにありました。そのことを踏まえれば、分析のさいに医師に対して患者が抱く特別な感情についてもまた、次のように考えることができるのです。そうした感情を生み出す用意は、治療を受ける前からすでに患者の心の中でされており、それが、治療にあたって医師という人物の上に“代わりに”転移されたのだ、と。
フロイトは次のように述べています。
「つまり、転移は、組織の新生と幹の肥大を生じさせる、樹木の木質と木皮の間の形成層にたとえることができます。転移がこのような意義を獲得した時にはじめて、それまでの患者の記憶を手がかりとした分析作業はぐっと後退するわけです。そうなれば、われわれが作業の対象とするものは、もはや患者の以前の病気ではなく、それに代って新たにつくり出された、つくり変えられた神経症であるといっても間違いではありません。」
「今、ここ」と「感情的なつながり」。100年前に作られた精神分析には、変わりゆく時代を生きる私たちが忘れがちなものが詰まっている。
傲慢でなく無意識を“翻訳”することは可能なのか? ましてやそれで患者を救えるのか? その答えはこうなのです。
転移により、治療者自身が患者の(リビドーの)対象となることで、それは可能である。なぜならば、第一に、治療者は患者の病気が新たにつくり出される様を、直接見てきたのだから。そして、第二に、転移によって医師に対し抱かれた愛情は、のちに医師が話す“翻訳”の内容を患者が受け入れるための、何よりも確かな支えになるから。
「今ここにあるもの」と「支えとなる感情」。どちらも、現在のように変わりゆく時代に、正解がない人生を生きる中で、つい忘れがちなものではないでしょうか。私自身、ちょっと振り返ってみるだけで、日々いかに過去の出来事にとらわれているか、そして、いかに未来を憂い不安にさいなまれているか、ハッとします。こんな態度をむやみに続けていれば、人との温かいつながりはなくなっていく一方でしょう。
フロイトは言います。
「〔転移によって生じた〕これらの新しい人為的な神経症の克服は、最初から治療の対象となっていた病気を治すことと同じであり、われわれの治療上の課題を解決することに通じます。医師との関係の中で正常となり、抑圧された衝動興奮の作用から自由になった人間は、医師が離れて行った暁にも、その個人生活はそのまま正常かつ自由であり続けるのです。」
生きている以上、過去から切り離されることはありません。しかし、だからといってそれにとらわれ過ぎず、まずは目の前のことに真摯に向き合い、ポジティブな感情で人との関係を築いていく。そうすれば、過去はおのずとその印象を変えていき、私たちを自由にしてくれるのです。
「他人と過去は変えられない」とよく言われますが、人生はそんなに単純ではないのかもしれません。人との出会いによって新しいものが生まれ、ひいてはそれが過去をも更新し、そのことによって未来が開けていく。フロイトが目にしていたのは、そんな複雑で豊かな世界なのかもしれません。
【参考文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 305-323.