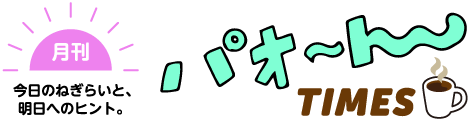
VOL 23|2025年05月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

61歳、男性。マンハッタンで自前のキャブを運転して約1年。以前は30年の間船の上で働いていた。インタビューをしたのは夕方、彼の勤務が終わった後。体が大きい彼は、見るからに疲れ切った様子でばたんと倒れ込むように椅子に座ると、靴を脱ぎ、つま先をもぞもぞとさせながら、「ああ!この足!」とため息をついた。
「貨物船ではコックをしていました。インドやアフリカへ行っていました。仕事は短時間で終わるものだったので、一日中デッキを歩き回っていました。楽しかったです。運動にもなりますしね。この仕事を始めてから20ポンド(訳注:約9キロ)も体重が増えました。
妻に海での仕事を辞めると約束したのです。一度、私がインドへの航行を終えて帰ってきたとき、一人でいるのはつらいから辞めてほしいと妻に言われたこともあります。私は「あと1年だけ待ってくれ」と言いました。私たちにはある計画があり、そのために貯金をしていたからです。結局その後またインドへ行って戻ってくるまで2年間続けました。私は自分の若さを海に捧げた後、家に戻り、その後の人生を妻に捧げたんです。
妻と私はお互いにいつも愛し合っています。何をするにも一緒です。夜中に起きてトイレへ行くときも一緒で、手を彼女の腰に回して、ダンスのステップを踏みながら廊下を歩いて行くんですよ。
どんなに妻を愛していても、海に惹かれてしまうんです。私と妻の夢は帆船を買って外国に住むことです。それが、貯金をしてきた理由でもあります。タクシードライバーもそのための手段であり、この年になろうとも、その夢を止めることは誰にもできません。」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 266-269.

~フロイト博士の処方箋~

上下巻からなる『精神分析入門』もいよいよ最後の章になりました。「1年経ったコメは動物のエサ」と言う政治家もいるこのご時世で、2冊の本を2年かけて読んでいます(笑)。
さて、時間がかかるといえば精神分析療法です。
前々回~前回に読んだ「転移」の章では、いわば「古くて新しい症候」が形成されることを見てきました。治療中、患者の心の中ですでに準備されていたものが、医師という対象を得て新たな症候として現れます。医師はその様子をじかに見てとりながら、内的抵抗を克服するよう患者を導き、病気の根本原因(無意識下に抑圧されたもの)を探りあてることで治癒へと向かわせます。
手っ取り早く得られた成果は長続きしない。時間をかけ、自分の心に誠実に追求されたものだけが、ほんとうの成果をもたらす。
症候が医師を対象にしているのならば、手っ取り早く医師の命令ひとつでどうにでもなるのではないか、と思うかもしれません。昔テレビでもよく見た催眠術のように、「あなたの苦しみなんて吹き消してあげますよ。(パチンと手をたたく)ほら!消えた!」といった具合です。
実は、フロイトは催眠療法に従事していたこともあったようです。結局、症候を表面的に覆い隠すだけの催眠療法では、たとえ効果が表れたとしても長続きはしなかったそうです。
患者を苦しめる根本原因を、しかも無意識の中から探りあてるのは、相当手間のかかることだと容易に想像できます。しかし、患者の心の中の現実と一致するような解釈にたどり着いたとき、葛藤の解決と抵抗の克服が達成され、患者は真の内的変化を遂げるといいます。その達成感たるや、それまでかけたどんな労力も吹き飛ばしてしまうであろうこともまた、想像に難くありません。
症候は、自我によって満足を断念させられたリビドーが無意識の中を徘徊し、そこから材料を得てつくり出されます。その症候を対象として、リビドーはどうにか「満足らしくもない満足」を得る一方で、自我は苦しみます。精神分析療法においては、そんな自我が、無意識的なものを意識化する解釈作業に取り組むことになります。
心の中の現実と照らし合わせながら時間をかけて作業を行ううちに、かつては無意識だった範囲にまで自我は拡大されます。その結果自我はリビドーに対して和解的となり、「リビドーに何らかの満足を快く与えてやろう」という気持ちになります。こうして、葛藤や抵抗は乗り越えられるのです。
分かり合えなさを超えて人は分かり合える。“真実は藪の中”でも、藪の中に分け入ることはできるのだから。
金原ひとみの小説『YABUNONAKA-ヤブノナカ-』では、「悪のような正義感」を持つと自認する作家、長岡友梨奈が登場します。物語が始まって間もなく、彼女は次のように独白しています。
「時代が緩かったのだ。私も木戸も、他の作家や編集者も、男も女も、緩み、弛(たる)み切っていた。出版業界だけではない。日本社会全体が、今ではとても許容されない数限り無い事例を、排除も糾弾もせず、ただ黙って包括していた。今、爪の先まで縛り上げられた、自分も含めた業界人を見ながらざまあみろと思うし、死んで償えとも思う。これが私の、悪のような正義感だ。」
結局、物語が進むにつれ、長岡友梨奈は正義感の名のもとにタガを外していき、破滅の道を突き進んでいきます。
「悪のような正義感」という倒錯した表現は、リビドーが症候によって得るとされる「満足らしくもない満足」と重なって見えます。フロイトによれば、神経症にまではならなくても、人間は皆「潜在的な神経症患者」として、何らかの抑圧と衝動興奮を抱えて生きています。そうである以上、私たちはつねに物事の裏面を想像する必要があります。たとえ不快なものでも、一面では快感なのかもしれないと考える必要があり、たとえ正しくても、悪いことなのかもしれないと考える必要があるのです。
『YABUNONAKA-ヤブノナカ-』は、互いに絡み合う多数の登場人物の視点で語られた物語で、同じ一つの物事に必ず付きまとう多面性と、それゆえの人間同士の分かり合えなさが明らかにされます。ただし、それは正確には「簡単には分かり合えない」ということであり、「手間ひまをかければ分かり合える」というフロイトの理論と矛盾するものではありません。
この作品の出版にあたって金原は「変わりゆくこの世界を、共にサバイブしよう。」というメッセージを添えています。容赦なく変わりゆくこの世界では、誰もが被害者にも、そして加害者にもなりえます。しかしその苦悩を時代や社会のせいにすることなく、結論を急がずに時間をかけて向き合っていきたいものです。その果てに訪れる自らの内的変化こそ、サバイブしたことの証に違いありません。
【参考文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 324-338.