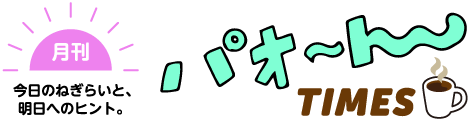
VOL 24|2025年06月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

26歳、男性。タクシードライバーの仕事を始めて4年が経過。曰く、「もともと、2年くらいで辞めるつもりだった。時間に融通が利くから、学校に通いながらでもできるなと思って始めたんだ」。
「認めたくはないけど、もう、タクシーの運転は前ほど新鮮なものじゃないよ。そういう瞬間は今でもあるにはあるけど、自分の姿勢や生き方みたいなものを決めるってことに関する限り、この仕事が世界で最も理想的とは思わないな。
この街を前からよく知ってたんだ。この街にいれば、面白くて、生き生きしていて、個性豊かな人たちと出会えるよ。あ、たまに、ハイになってやけにおしゃべりな人たちもいるけどさ…。この仕事を始めてすぐの頃は夜の11時まで働いてたよ。今は厳しく管理していて、朝の7時半頃から夕方5時までにしてるけどね。
チップをもらえないからって怒ったりはしないよ。怒るドライバーはたくさんいるけどね。タクシー代を払うだけで精いっぱいの人もいるって分かってるから。ただ、チップを払う余裕がないだけなんだよ。かなり荒れてる地域に住んでいて、歩くよりもタクシーに乗る方が安全だという人もいるし、最近移民としてやってきたばかりで、こっちの習慣に慣れていない人もいる。プエルトリコ人はチップを払うけど、メキシコ人は払わない、とかね。習慣の問題なんだ。自分が彼らにそれを教えるべきだとは思わない。他のドライバーがやるんじゃないかな。
間違いなく言えるのは、高級住宅街に住む人やビジネスマンが一番良いチップを払うわけじゃないってことだね。一番良いのは、その辺で乗せるブルーカラーの人たちだよ。」
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 269-274.

~フロイト博士の処方箋~
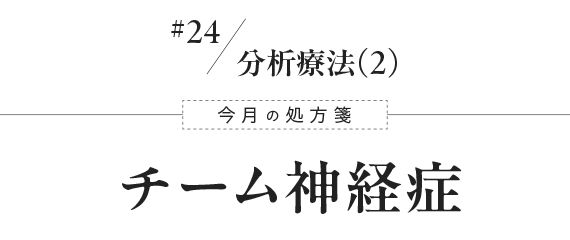
出自などにとらわれたラッパーたちのこじれたビーフを余裕で蹴散らすような「チーム友達」のリリック。
「契ろう 契ろう 契ろう 契ろう」とたたみかける言葉は、分断の進む現代社会で誰もが求めていたメッセージであることを、楽曲の世界的ヒットが証明しました。
ところで、フロイトもまた、このようなマインドだったと言えます。
その類似性は、「チーム友達」は「チーム神経症」に、「契ろう~」は「リビドー リビドー リビドー リビドー」に、すらすらと置き換え可能なほどです(笑・自分で書いていてくだらない)。
健やかな日々のために、心のエネルギーの「質」ではなく「量」に目を向けてみよう。
症候の正体や、その背後にある無意識を知る手がかりとして「夢」に着目したフロイト。その中でわかったのは、神経症患者と正常者の夢は本質的に少しも違っていないということでした。
健康な人もまた、心の中に夢を、ひいては症候を形成するだけのものを持っている。つまり、健康な人もまた何らかの抑圧を行なっていて、その抑圧を維持しつづけるためにエネルギーを消費しながら、抑圧された衝動興奮を内に秘めている。そして、彼らのリビドーの一部分もまた、彼ら自身の自我の支配を免れていることがわかったのです。
手に負えなくなったリビドー(そして、それがつくり出した症候)に悩まされる神経症患者。彼らと私たち健康者はあくまで地続きであり、あるのはただ、自我の支配を免れたリビドーに対しどのくらいエネルギーを使っているか、生活を楽しめなかったり、仕事ができなかったりするほどのエネルギーを使っていないかどうか、という違いだけです。
フロイトは、このようにして、心の問題を「質」の問題から「量」の問題へと変換しました。こうした捉え方は、私たちが日々健やかに生きるうえで欠かせないものではないかと思います。
なぜなら、心のあり方は質ではなく量の問題であると考えれば、「正しさ」を求めることはなくなり、より生きやすくなるからです。昨今は「論破ブーム」などもありますが、そんなふうにどちらが正しくてどちらが間違っているかを追求することなど、何の意味もなくなります。
心の持ちようは結果ではなく原因。目の前のできることから手をつけてみよう。
客観的な良し悪しではなく、まずは現実的な結果、すなわち自分の生活や仕事を振り返ってみる。もしそれらがうまく回っていなかったら、心のエネルギーをより多くそれらに充ててみる。そのときも、これで正しいのかな?などは気にせず、目の前のできることから手をつけてみる。
なんてことないと言われればそれまでですが、フロイトに従えば、経済論的にこっちが増えればあっちが減る、ということになるはずなので、あれこれ考えずそれだけでいいのです。
治療のための作業を行う「戦場」は、「必ずしも敵の重要な城砦の一つである必要はありません」というフロイトの言葉が印象的です。以下に引用してみましょう。
「かりにわれわれが、医師に対するつよい父親転移を作り出し、ついでこれを解消することによって幸いにしてその症例を治すことができたとしても、その患者が以前に父親へのリビドーのこのような無意識的結合のために病気になっていたのだと推定するのは、間違いであるかもしれません。父親転移は、われわれがリビドーをわがものにしようとして戦う戦場にすぎません。患者のリビドーは、他のもろもろの位置からそこへ導かれてきているのです。この戦場は、必ずしも敵の重要な城砦の一つである必要はありません。敵側の首都の防衛は、なにも都門の前で行われるには及びません。転移が再び解決された後にはじめて、病気中のリビドーの配分を頭の中で再構成することができるのです。」
心の健やかさは、結果ではなく原因です。すべての“はじまり”と言ってもいいでしょう。そんなはじまりを整えるのに正しいも間違っているもないし、重要かそうでないかも問題ではない。まずは手をつけてみよう。はじまりが整えば、過去のできごともきっと冷静に反省できるようになる。言われてみれば当然のことです。
心を携えて日々を生きる私たちの“戦場”は、いつだって今、ここにある。その意味で誰もが仲間であり友達である。そのことをいつも忘れないようにしたいものです。
【参考文献】
ジークムント・フロイト著、井村恒郎ほか訳
『改訂版フロイド選集2 精神分析入門〈下〉』(1970年、東京:日本教文社)
pp. 324-347.