
VOL 25|2025年08月号

~時代と海を超えた、はたらく人々からの手紙~

47歳、男性。シカゴでバスの運転手として働いて27年目。夜間のシフトで勤務しており、日中に2時間半の休みを取ることができる。日曜日、妻も同席する中で話を聞いた。
「初めは良い仕事だったよ。黒人の採用が始まって2度目のときに僕も入ったんだ。1945年のことだ。
戦争が終わってすぐだった。不景気から脱け出して良い仕事にありつけた、偉大な一歩だったわけだ。今でも覚えてるよ。シカゴ交通局で働くようになった黒人の私が、日曜日、礼服の代わりに制服を着るようになったんだ。その制服にはそれだけの威信があったからね。アイゼンハワージャケットみたいなデザインで、行事や冠婚葬祭の時に着ていたよ。今じゃもうそんな感覚はなくなったけどね。25年前の話だ。
以前は切符も切ったし、釣銭の用意もしたし、そんなことを同時にやりながら運転もしていた。怪しげな乗客が乗ってきたら、気を張りつめてた。もしかしてあいつはピストル強盗じゃないだろうかってね。
でもしだいに、自分たちが見張られる側になった。見張り役が乗客に扮して乗ってくるようになったんだ。彼らは車内で起こることすべてに目を光らせていて、もし僕らが何か間違ったことをしたら、2~3日後に事務所から呼び出しを食らうことになる。僕も一年くらい前に呼び出されたよ(笑)
それから、路上にも監督者が配置された。彼らは車に乗っていて、僕らが予定時刻よりも早く運行していたらそれを書き留めて、後日事務所へ呼び出しさ。時々路上で停車させられることもあって、そんなときはほんとに参ってしまうね。
仕事が終わったら、ちょっとその辺で座って話でもしたいなってなるのが普通だよね。でも僕はとにかくすぐに職場から出て家に帰りたい。僕はただ、朝起きて、そこへ行って、そしてそのことについて何も考えないってことをひたすらやってるだけだよ。機械のようにね。そんなふうにしか感じられないな。」
~今月のリアルヴォイス~
“It was a giant step coming from the Depression into a good job.”
(不景気から脱け出して良い仕事にありつけた、偉大な一歩だったんだ。)
*a giant step=偉大な一歩、*the Depression=不景気・恐慌
【出典】
Studs Terkel,
Working: People talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do,
New York: Ballantine Books, 1985, pp. 274-279.

~フロイト博士の処方箋~
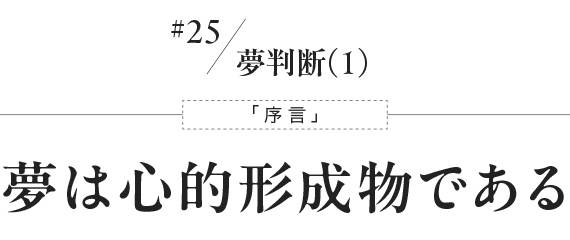
医師として神経症の患者に向きあい、精神分析の手法で治療を試みるフロイト。この『夢判断』の序文で次のように書いている。
「夢は、心理学的に吟味してみると、一連の異常な心的形成物中のいちばん最初のものであることがわかる」。
「いちばん最初」とあるが、これは、実際に彼が臨床で向きあう症状を「最後」とした場合の「最初」である。つまり、夢は実際的(臨床的)意義をもたないかもしれないが、それだけによりいっそう理論的価値は大きく、必ずや臨床的成功につながっていくとフロイトは考えているのだ。
自分が見た夢の話を誰かにしたことがある人は多いだろう。しかし、それはあくまで“人に話すことのできる夢”だったはずである。その裏では誰もが、そうではない夢もたくさん見ている。とてもじゃないけど人に話せないような、恥ずかしい夢、おぞましい夢、目覚めると同時に霧散した夢・・・。
フロイトはこの著作の中でさまざまな夢の実例を紹介していくことになるのだが、それらはどれも、簡単に“人に話すことのできる夢”ではない。そのような夢は、きわめて神秘的な人間の精神をすこしでもときあかそうとする彼の目的に役立たないのである。
“人に話すことのできる夢”、すなわち、文献に記録された夢や、見知らぬ人から収集した夢を考察の材料にはできない。そこで、彼が材料としたのは、彼自身の夢と、彼が精神分析治療を行った患者たちの夢だった。ただし、患者たちの夢は、そもそも神経症の影響を受けて複雑化していて、むやみやたらに使用できるわけではなかった。また、フロイト自身の夢についても、いくら彼が自分の気持ちを押し殺してさらけ出そうと努めても、やはり限界はあった。
みずから、「(自分の夢を取り上げようとする場合、)省略や入れ換えなどによって多くの秘事をぼかしたいという誘惑に抗しえなかった」と断りを入れつつ、とにもかくにも夢という大海原に果敢に漕ぎ出していくフロイトなのであった。
【参考・引用文献】
ジークムント・フロイト著、高橋義孝訳
『夢判断(上)』(1969年、新潮社)
pp. 7-9.